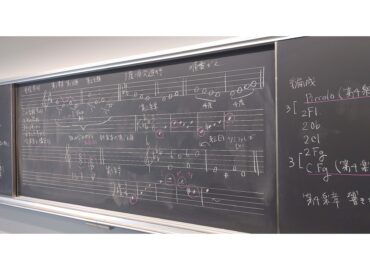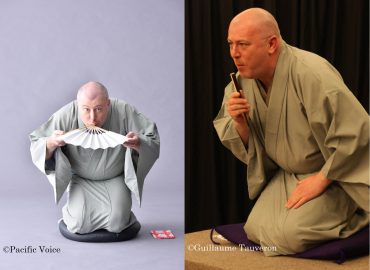音楽を学ぶきっかけと経験
私は6歳の時に音楽に興味を持ち、9歳で正式にチェロを習い始めました。当時、中国国内の経済状況はあまり良くありませんでしたが、両親は1ヶ月分の給料を使ってチェロを買ってくれました。それが私の興味を支えてくれました。
Q:ご家族は音楽をとても大切にしていたのですね。他のご家族も音楽を学んでいたのですか?
はい、姉はバイオリンを学び、弟はフルートを学びました。それぞれ自分の好きな楽器を選びました。私がチェロを選んだのは、その深くて重厚な音色に魅了されたからです。

中日の音楽教育の違い
Q:80年代日本に留学し、日本で音楽を学ばれましたが、中国と日本の音楽教育にはどのような違いを感じましたか?
中国の音楽教育は成果を重視し、成果を早く出すことを好みます。先生は生徒に厳しいことが多いです。一方、日本では基礎や細部を重視し、個々の個性やペースを尊重しながら励ましてくれます。
Q:それは音楽だけでなく、スポーツなど他の分野でも同じようですね?
そうですね。中国はエリート育成に重点を置き、優秀な一部の人を選び出すことを重視します。一方、日本は全員が参加し、興味を育てることを重視します。

才能と努力について
Q:音楽といえば、多くの人が「才能が大事」と考えますが、どう思いますか?
実は、子供の頃は先生に「才能がない」と言われました。でも、才能は一部に過ぎず、努力がもっと重要だと思います。私は継続と努力を通じて、東京交響楽団に入団し、国連でも演奏することができました。
Q:そのような粘り強さは本当に素晴らしいですね。でも、日本の教育は他人と比較しないことも強調しているのですか?
そうです。日本の教育は個人の特⻑を尊重し、生徒は自分自身との比較に集中するよう教えます。他人と競うのではなく、自分の成⻑に集中することを学びました。

基礎と創造性のバランス
Q: 最近、多くの人が基礎を固めずに、直接創作や現代的なスタイルの表現を求める傾向がありますが、どう思いますか?
作曲に関しては、統一された基準はないと思います。基礎が不十分でも評価される作品を作れるな ら、それも一つの才能です。ただし、しっかりした基礎があることで、作品に深みや質が生まれるのは事実です。
Q:日本の学生は創造に関する自由度が高いですか?
そうですね。日本の教育はラベルを貼らず、自由な探求を奨励します。しかし、中国ではランク付けや分類が多く、生徒の創造性を制限する可能性があります。
Q:音楽を学んで得られた最大の成果は何ですか?
技術の向上だけでなく、創造力や想像力も養われました。また、細部に注意を払う力や、見落とされがちなものを発見する力も身につきました。これは他の分野でも役立っています。
Q:その力はその後の人生やキャリアにも影響を与えましたか?
はい。音楽は粘り強さを教えてくれただけでなく、外部の評価から解放され、内面的な探求に集中する力を与えてくれました。その結果、人生やキャリアにおいて独立性と創造性が高まりました。

記憶に残る演奏会
Q: 先生の記憶に残る、または一番満足した演奏は何ですか?
数が多すぎて一概には言えませんが、ウィーンの⻩金ホールでの演奏が特に印象深いです。リハーサル中、他の人が休憩している間にホールに一人で残り、練習をしました。その時、ホール全体がとても透き通った音響空間で、本当に素晴らしかったです。その舞台は数百年の歴史があり、床も弾力があって、全体の雰囲気がとても良かったです。本番の日は満員で、ブラームスの交響曲第4番を演奏しました。本当に忘れられない体験でした。
Q:⻩金ホールは確かに憧れの場所ですね! 別な演奏経験はありますか?
上海での演奏も印象に残っています。その時、日本の友人がたくさん来てくれて、20束以上の花を持ってきてくれました。日本の人たちは花束にかける予算が高くて、花束がとても大きかったです。抱える のが大変で、最後には花を担いで下ろしました。その後、花束は楽団の同僚たちに分けましたが、みんなとても喜んでいました。
Q:先生は日本で音楽活動をしてとても幸せそうですね!
はい、日本の音楽環境はとても自由です。日本での仕事の状態はとても快適で、興味を職業にできたことを本当に幸運だと思います。
(インタビュー:2024年11月)