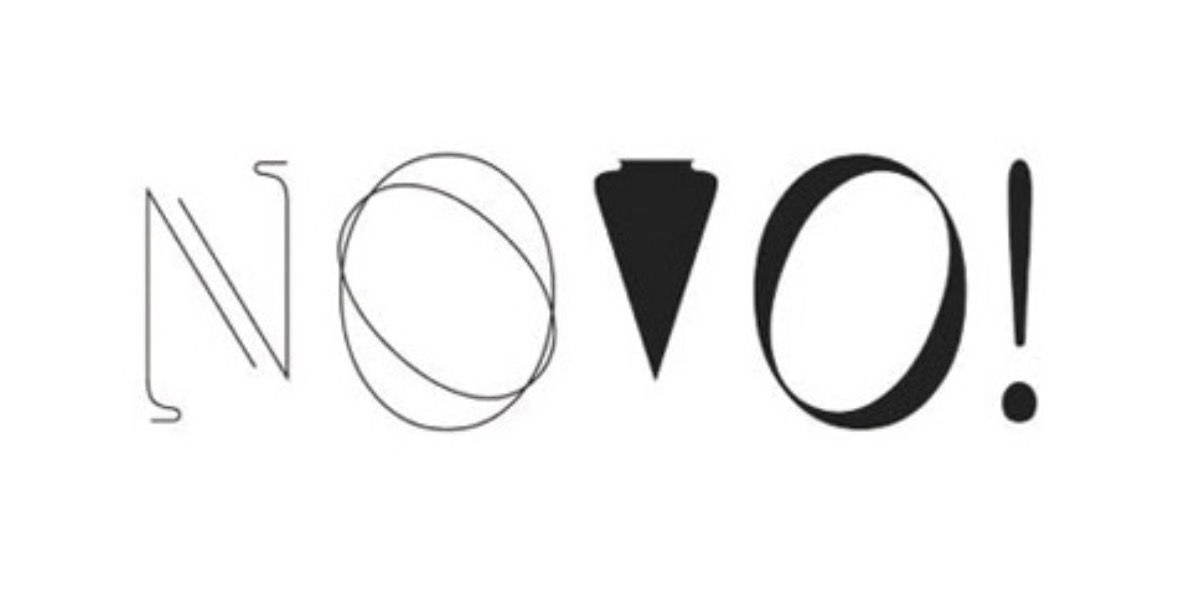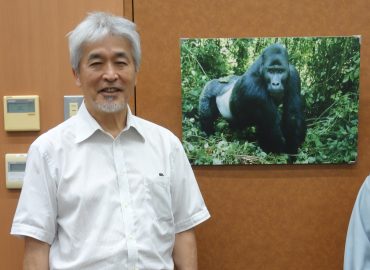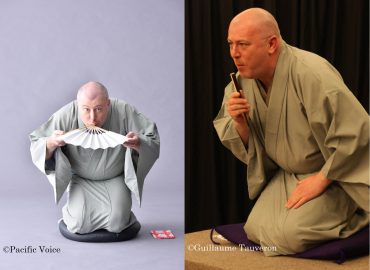Q:まずは、KATOさんの現在の活動について教えてください。
古着を売ったり、クラブでパーティーを企画したりしています。
Q:古着とクラブという組み合わせはユニークですが、きっかけは何だったのでしょうか?
最初は古着屋を店舗で経営していたんです。お客さんの中に音楽にとてもマニアックな美容師の方がいて、その人がDJもやっていました。その方が「パーティーで服を売ってみたら?」と提案してくれて、一緒にやってみることになったんです。
Q:クラブにはもともと馴染みがあったんですか?
いや、全然(笑)。自分はクラブなんて一度も行ったことがなかった人間でした。でも、その美容師さんが私の古着を気に入ってくれて、それをクラブのパーティーで売ろうという流れになったんです。

KATOさんが営む古着屋
Q:最初に服を販売したのはどんな場所でしたか?
原宿にある「bonobo」というクラブです。2階が座敷になっていて、そこに服を並べて、みんなで座りながら見られるような形でした。当時の店舗ではコレクタブルなヴィンテージを扱っていて値段も高かったんですが、クラブでは気軽に買えないと思ったので、3000円くらいの商品を大量に仕入れて販売したんです。そしたらびっくりするくらい売れて…。「クラブイベントってこんなに服が売れるんだ!」と衝撃でしたね。
Q:そこからパーティーの企画へと広がっていったんですね。
そうです。2年で10回ほど、その美容師さんとイベントをやりながら服を売っていました。そのうち、通っていたFORESTLIMITで毎週行われていた帯パーティーのひとつがなくなると聞いたんです。そこで「じゃあ自分がやってみたい!」と言って始めたのが、今やっているパーティー“K/A/T/O MASSACRE”の原点です。
Q:最初から毎週開催しようと決めていたんですか?
はい。毎週やった方が面白いし、ちょっとおかしいじゃないですか(笑)。最初の30回くらいはほとんどお客さんが来なかったんですが、それでも楽しかったですね。
Q:パーティーを続けていく中で、音楽についてはどう関わってきましたか?
最初は音楽のことは何も知りませんでした。でも、パーティーは音楽そのものを楽しむだけではないと思っています。例えば50人集まれば、互いに考えが違う人もいるかもしれない。でも、それも含めて共生している状態で、それこそがパーティーの面白さなんじゃないかなと思います。
massacre vol.537 について
※新谷啓が実際にパーティーに伺い、KATOさんにお聞きしました。
Q:7月23日の「massacre vol.537」について伺います。今回はどんな意図で企画されたのでしょうか?
世界的に社会が右傾化している中で、ユースの表現や在り方が無意識にも敏感に反応していると感じていました。例えばファッションやラップのリリックなどですね。今回はそうした社会や若者の感覚を意識しつつ、新しいムードに敏感な、ある意味ファッション性の強いラインナップにしました。
Q:実際に開催してみて、どのように感じましたか?
10代の子たちは同世代や同じコミュニティ以外の表現にあまり関心を示さない傾向があって、それが興味深かったです。年々、コンテクストよりもコミュニティを軸にブッキングする方が成功しやすく、参加者の満足度も高いと感じています。これは社会や人間心理の保守化も映していると思います。
割とコンテクストが複雑な面もあり、他の回よりも伝わりづらい内容かな、と思いつつ開催した挑戦的な回で、実際そのため集客が厳しい面もありつつだったのですが、そういう厳しい状況の中でやってると、意図を感じて来てくれた人への有り難みとか、感謝の気持ちがより強く感じられて良かったです。
Q:それは今の社会状況とも関わっていると。
はい。社会が絶望的になり、自己肯定感も得づらい状況では保守化は当然の流れだと思います。そういう中で若者の感じてるムードは、右だろうと左だろうと、いつだって素直で、実生活の不安や喜びに正直な気がします。だからこそ、それに寄り添って支援できるような在り方を模索したいと思っています。
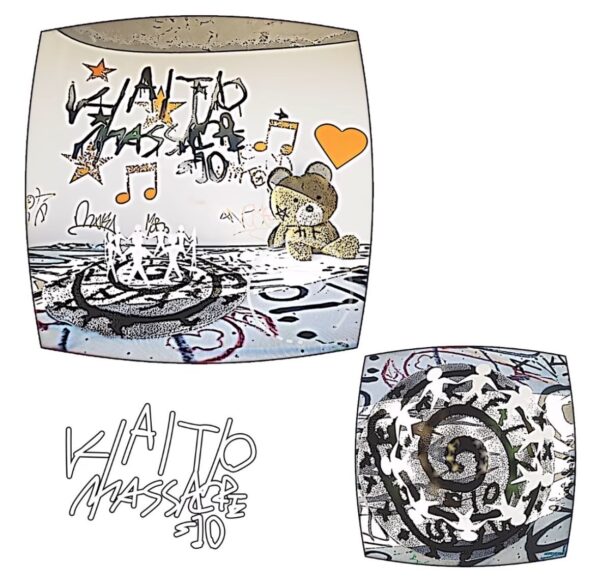
MASSACREのフライヤー
コロナ禍での新たな試み
Q:コロナ禍ではどんな取り組みをしましたか?
最初は手探りで、インスタライブやZoom、アバター出演など、毎週開催を止めない為にも、とにかくできることを全部やりました。その後Twitchを使うようになり、カメラ1台で配信する形に半年ほどで移行しました。そのシステムを組んだのはFORESTLIMITのオーナーのナパーム片岡で、彼が独学で構築してくれたんです。私はパーティーをやって、彼は音響とシステムを支える。そんな関係性ですね。
Q:新しい人との出会いについてはどう感じていますか?
開催する場所は決まってるからこそ、常に新しい人を探すのは必要です。でもそれ自体が楽しいんです。新しいものに出会えるわくわく感がありますからね。

コロナ禍でアバターを使った開催の様子
商業性と面白さのバランス
Q:パーティーの運営において、商業的な面と面白さのバランスはどう考えていますか?
どんどんステップアップして大きくなっていくというようなこと、それは目指していません。たまたまFORESTLIMITと出会って、流れで今のような状況になってるだけなので、あくまでFORESTLIMITに還元できたり共に歩んでいける形を目指してます。ただ、パーティーの収益は活動費になっていて、収益がないとそもそもいろんなパーティーに行ったり交流機会を失っちゃう。だから、ある程度収益を上げられる結果にはしないと、と思ってます。
商業的に利益を出すことと面白さの追求のバランスが難しいなと思いますね。
こうすればもっと人がくるだろうってアイデアも浮かんだりするけど、それだと別に自分がやらなくてもよいのでは、と思う事もあったり。なにかしら違う要素を入れたり、違う要素を入れるけどある程度人が来るようにしたり、そういったバランスをとにかく考えます。
色んなイベントに行ってるとそのイメージが湧きやすくなりますよね。それがふわっと頭の中に残るから、いざ考えてる時には組み立てやすくなります。

都内某所にてインタビューを行った際の様子
信頼関係の築き方
Q:演者との信頼関係を築く上で意識していることは?
音楽性だけでなく、演者同士の関係性やコミュニティ等もある程度把握して、「この人とこの人なら楽しめるかも」とか考えたりもしますね。
会ったことのない人同士を組み合わせるときは、こちらも慎重にやんないといけないと思ってます。誘われた人は引き受けてくれるけど、内心やりづらいなとか、そういうの可哀想じゃないですか、単純に。楽しんでもらいたいし。
自分がどういう意図でラインナップ組み合わせたかをタイムテーブルも含めて最初の時点で話すようにもしています。
演者の方同士は全然関わりのないパターンもあるし、関わってるパターンもある。
アーティストひとりがいたらその周りにファンだったり仲間だったりがいるわけです。その人らがパーティを形作る。それらが上手く融合して楽しめる空間を作る。そういう全てのバランスを気にしないとあまり上手くいかない。
でも大体一般的なパーティ作りって、演者同士が仲良い状態でブッキングするから、必然的にみんな仲が良い。そりゃ楽しいだろうし良い形になるんですけど、自分はそれに異なる要素を入れようとしちゃうから、異なる要素を入れるんだったらそれ相応の工夫を努力しないと無責任だと思ってます。
Q:信頼を得るために具体的にどんな行動をしていますか?
その人のイベントや出演にとにかく足を運びます。知らないオーガナイザーに呼ばれても不安だと思うんです。「加藤ってなんなの」ってなるわけだし。でも何度も会って、少なくとも応援してくれているとわかれば安心できますよね。時間もお金も労力もかかるけど、私の場合は現状はこういったフォローが生活に完全に組
パーティの収益がその資金になってるので、みんなにもらったものをそのまま返してるだけなんですよね。
パーティーへの思い
Q:オーガナイザーという立場についてどう思っていますか?
私が元々オーガナイザーっていうものに抱いてる思いって昔はわりかしネガティブなものだったんです。アーティストやお客さんが支えてくれているからパーティーが成り立っているのに、オーガナイザーが偉そうに見えてしまう偏見があった。でもだからこそ反面教師にして、演者の方にちゃんと信用してもらいたいと思って行動しています。
お互いが信用し合うって幸せなことじゃないですか。
パーティーに誰かを呼ぶというのは、不思議と面白いものだなぁと、続けていく中で思うようになりました。
Q:パーティーに呼んだ人が活躍していくと、やはり嬉しいですか?
そうですね。「この人は面白そうだな」と思って呼んだ方が、その後活躍されていたりすると、「やっぱりな」と嬉しくなることもありますね。

イベントのスナップ
パーティーの立場と社会との関係
Q:パーティーが果たす役割についてどう考えていますか?
パーティーは村の公民館のようなものだと思う事もよくあって。そう考えると、集まる時に相手がどういうことを考えているのか知る必要がある。同じ場にいることで人がどういうことに安心したり、不安に思うのかを想像できたりする。
ただでさえ今の社会は異常な変化をしていて、特に若い人は「こういう考えでないといけない」という外圧に晒されて生きているような気がしています。
だから、せめてパーティーに来ている時くらいは安心して気楽に楽しんでもらえたらいいなとは思ってますね。
Q:最後に、パーティーを通して目指していることを教えてください。
人のことを分かった気にならないからこそ解りたいのかなぁと思います。
「同じ場を共有して同じ場を創る。」
パーティーのすごいところかも知れませんね。
自分は人のことを分かっているとは思っていません。
だからこそ、分かりたいと思っているというか。わからないとしても、同じ場を共有して場を作ることで、共生の可能性が見えてくるのかなと思っています。
分かり合えなくても、パーティという場を通じて共生している状態は、良い社会の状態だと考えています。
(インタビュー:2025年6月)