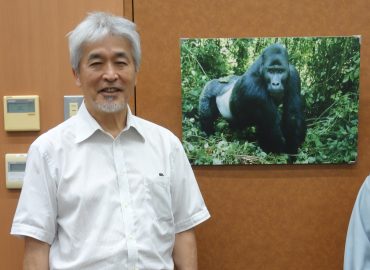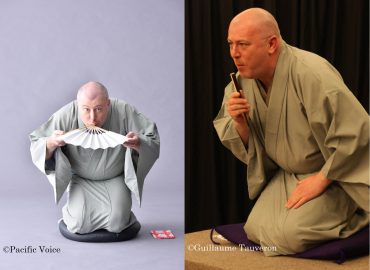チョウの保全活動を始めたきっかけ
私がチョウの保全活動を始めたのは、単純に「なんとかしなきゃ」と思ったから。小さい頃から虫とか自然が好きで、いろいろな生き物を見たり調べたりしていたのだけれど、そういう環境がどんどん悪くなっていくのを体験した。そして、絶滅しそうなチョウも増えてきて、このままだと、チョウやその他の生き物たちが本当にいなくなってしまうという危機感を持った。
研究者になることも考えていたが、研究も大事だけれど、そもそも生き物がいなければ研究すらできなくなってしまう。だからまずは「守る」こと、つまり行動することの方が大事だなと思い、この活動を始めた。自然が好きな人は結構いるけれども、実際にそれを守るために行動する人はそれほど多くない状況だった。私は、「だったら自分でやるしかない」と思い動き出した。
高校の頃には、地域の自然を守るグループにも入り、大学に入った頃(ちょうど1992年頃)には、ブラジルで地球サミットが開かれるということから、日本全体で環境問題が盛り上がっていて、学生の活動も始まっており、私もそうした若者の環境団体(A SEED JAPAN)にも入り、環境問題全体についての活動も行った。そうした活動を通じて、環境活動についてもより身近に感じるようになった。
その後、大学の修士課程で、絶滅の危機にあるチョウの保全の研究を行い、その後は就職等をして働いていたが、チョウの状況はさらに悪化しており、それを何とかするために、日本チョウ類保全協会*を立ち上げた。とにかくチョウの絶滅を防ぐために、絶滅危惧種の保全に力を入れ、これまで取り組みを行ってきた。今でもこれは変わっておらず、絶滅危惧種を具体的に守る活動が協会の活動の軸になっている。
最近では、絶滅危惧種のチョウばかりでなく、身近に普通に見られるチョウの状況も悪化してきているため、チョウを調べて自然環境の変化を知るための市民参加型のチョウのモニタリングプロジェクトを開始した。全国各地をまわって、研修会を行い、ボランティアの力を借りて、自然のようすを地道に記録している。調査には「トランセクト調査」という方法を使っていて、決まったルートを定期的に歩き、観察できたチョウをそのつど数えていく。それを続けていくことで、すごく信頼できるデータがたまっていく。チョウのモニタリング調査は特にヨーロッパで進んでおり、この調査と同じように行うとともに、ヨーロッパのプロジェクトに参加させてもらっている。
環境保全というと理系の分野に見えるけれど、実はめちゃくちゃ社会的な活動。だから調査だけをしていてもダメで、やっぱり身体を動かして社会に働きかけを行っていかないと、何も変わらない。評論家みたいに言うだけじゃダメで、自分で動くこと、それが一番大事だと思う。
*日本チョウ類保全協会
活動のやりがい
活動の範囲はかなり広く、北海道から九州まで、それぞれの地域で、地元の人たちと協力して活動することが多い。もちろん、私たちの団体だけで動くこともあるけど、やはり地域の自然はその地域の人々と一緒に守っていくのが一番なので、基本的には地域の人たちに、ご理解、ご協力をいただいて保全活動を進めている。調査とかデータを取るのももちろん大事だけれど、人と関わるのが楽しいし、そこにやりがいを感じている。

北海道でヒメチャマダラセセリを保全するために作業する様子(中村さん提供)
手伝ってくれる地域の人たちは、チョウそのものがもともと好きで、活動に参加している人が多いわけではなく、どちらかというと「自分たちの地域の自然を残したい」とか、「昔より自然が減ってるから、なんとかしたい」という思いで来てくれている。それはすごく嬉しいし、こちらの力にもなるよね。
やはり、共感は大事。みんなの気持ちが集まって動いてるというのが、この活動の一番の力になっているし、NPO法人の意味だと思う。
チョウを守る理由
こういう活動をしていると、よく「チョウを守る意味はあるんですか?」「チョウを守ると、私たちに何か利益はありますか?」とよく聞かれるんだけれど、チョウが一種絶滅したからといって、人がすぐに何かで困ることはないだろう。チョウは例えば植物の花粉を運ぶといった生態系の中での役割を持っているが、何種類かのチョウがいなくなったからといって、他に代替する生物もいるため、自然のバランスが大きく崩れるわけでもない。たとえば、今は生物多様性の危機の時代になっていて、カワウソやオオカミなどを代表として日本でもすでに多くの生物種が絶滅している。世の中では、それで人間が困ることはないって考える人もいるけれども、それは少しおかしいと思う。その考えを進めていくと、人間に直接利益のある生き物(家畜や作物など)だけいればいいやという考えも出てくる。しかし、それで良いのかという話になる。
都会の中でも近所の公園をちょっと詳しくみてみれば、植えてある樹木だけではなく、鳥や昆虫など10種、20種の生き物が普通にいるわけで、それだけでも人間の10倍、20倍の数の種の生物がいることになるよね。今は人間が地球を支配しているかもしれないけど、人間は所詮1つの種の生き物。それなのに、人間一種が好きなように自然環境を破壊したり、他の生物を絶滅させたりしてもよいのか?って。
人間も地球の一員なんだから、もっと謙虚になって、節度を持ってやるべきだと思う。隕石が落ちて恐竜が絶滅したみたいなことは仕方ないけれど、今のやり方はちょっと違うよね。ほかの生き物も生きる権利があるのに、それを人間が好き勝手にしていいわけがないと思う。
だから、チョウを守る意味があるのかというふうにとらえること自体、他の生き物たちのことを人間にとっての損得だけでみているということだろうと思う。いわゆる人間中心主義の考え方になるが、それで本当に良いのだろうか? 自然や他の生き物のこともしっかりと考えないといけないのではないか。ただ、もし「他の生き物が絶滅しても全然かまわない。人間だけの利益を考える」という風に社会が進んでいくのであれば、最終的には、地球のあらゆる資源を枯渇させてしまうとともに、他の生き物が住めないような状況になってしまうだろう。地球に住めなくなったら次は火星にでもいけばいいという考え方もあるが、それでよいのだろうか?
この話を人間と人間に置き換えて考えてみると、他人を搾取して、一部の人だけが幸せになるというような社会はおかしく、現代の社会でも富の不均衡(格差)といった問題が起こっている。このように格差社会や搾取によって一部の人だけが得をしているということを、人間と他の生き物という対比でも考えて欲しい。人間も地球に存在する一つとして、自然や他の生き物と共存しながら、節度を持って生きていくべきじゃないかな。もし人間中心主義に偏ってしまうと、すべて利益だけを追い求める社会になってしまう。

ヒョウモンドキ(中村さん提供)
現代社会を生きるわたしたちへ
生物多様性だけではなく、他にもいろいろな社会的な問題が現在山積している。それこそ今、地球の気候変動はどんどん悪化している。温室効果ガスを減らす努力も確かにしているけれど、現在の取り組みは根本的な解決にはまだまだほど遠い状況で、温暖化の程度を1.5℃以内に抑えるという国際的な目標の達成が非常に厳しくなっている。「地球温暖化(気候変動)はデマだ」という人もいるが、石油という化石燃料を大量に使っていて、よくこんな風に考えられるなと不思議に思う。気候変動の問題は、特に進んでしまうと、後々では取り返しがつかなくなる問題であり、一度進んでしまうと元に戻すことは不可能に近い。こうした問題は、最悪のケースを想定して対策をとることが非常に重要であり、予防原則が何よりも大事であるよね。
特に、地球温暖化(気候変動)の問題は、交通事故のような問題とは違って、一部の人だけが被害を受けるようなレベルの問題ではない。最近、異常気象による洪水などで日本でも一部の地域で大きな被害が出て、その地域の住民が悲惨な状況になっているというニュースをみることが非常に増えてきているが、これがさらに進んで最悪の事態となってしまった場合、全人類70億人が生活に困ってしまう危険もあるわけだから、後から都合のいい言い訳をすることでは済まされない。確かに地球温暖化の進行を防ぐためには、人の生活を大きく見直す必要があるだろう。しかし、地球で人が長く安全に暮らしていくためには、人間が地球の中でどのように暮らしていくべきか、一人一人が考えていく必要があると思う。

未来のことは100%こうなると予測できるわけではないため、だからこそ、都合のいい情報が流れがちになり、それを信じてしまうのは非常に危険である。今はSNS等で様々な情報が届きやすく、その中には誤った情報や解釈の間違いも多く、さらには悪意を持って情報を流している人もいるので、注意が必要である。だから、一人一人が自分自身で考え、正しい情報かどうかを見極められるようになっていく必要がある。
(インタビュー:2025年6月)