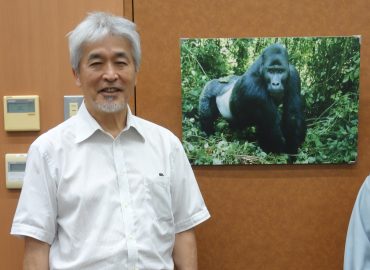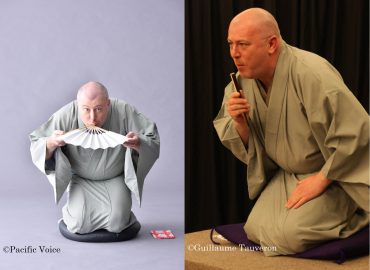編集や書店の仕事を経て、森林組合で林業へ転業、森林組合で経験を積み、その後2006年7月に仲間と共に東京チェンソーズを創業。山に入り林業現場の仕事から、広報まで幅広く担当。森の資源を無駄なく活かしながら、都市と森をつなぐ新しい林業のカタチをつくっている。「子供が将来、仕事を選ぶとき、林業も選択肢に入るようにしたい」という木田さんの言葉からは、林業への深い愛が伝わってくる。
林業を子どもの将来の夢にするために

Q:木田さんはなぜ林業の世界に飛び込もうと思ったのですか。
前は雑誌を作る仕事をしていました。ある雑誌を見ていたときに、山の仕事っていう特集があって、30代から転職して、林業を今やっていますっていう人が載っていたんです。そこで初めて林業っていうのは、転職してできる仕事なんだということを知りました。当時やっていた仕事も面白いは面白いんだけど、もうちょっと別な仕事もやってみたい気がしていた時期でもありました。自分1人が林業に就くことで、山の手入れ不足が解消されるわけではないですが、その流れを変えるきっかけになるかもしれないし、森とか山というでっかい存在を間に置くことで、お客さんも自分もお互い気持ちが和らぐかなと…そういう仕事って自分にあっていそうな気がしていて、やりたいなと思いました。
Q:東京チェンソーズを4人で立ち上げた理由やきっかけを聞かせてください。
立ち上げ直前は地元の森林組合にいて、そこにいた4人が独立して立ち上げたんですけども、まだその頃30代でなんとなくいろいろやれるんじゃないかみたいなのもあったんですね。森林組合の方がそこそこ大きい組織なので、そういうところから出て、自由に、自分たちで考えるようなやり方で、やっていければと思って独立しました。

東京チェンソーズ設立当時の4人(写真提供:東京チェンソーズ)
Q:独立して具体的にやりたいことが、当時からあったのですか。
林業って職業だとあんまり思われないんです。例えば子どもたちが将来やりたい職業はなんですかと言われて、林業とこたえることはまずないと思うんですよ。その選択肢に入りたいなって。森林組合では主に切り捨て間伐をやっていました。山に植えられている木の30%を伐るということを、全然持ち主と顔を合わせることもなく、流れ作業的にどんどんやっている感じでした。せっかく50年ぐらい前にそこの持ち主の先祖が何か目的があって植えているのに、そういうのを考慮せず、ただ一律に30%伐るみたいなのは、すごくつまんないなあと思いました。持ち主の話を聞いて仕事をしていく方が楽しいなと思って、そういうスタイルをやりたかったんですね。林業は自分たちだけじゃ完結しないので、後に続く世代も、林業をやりたいと思ってもらわないと、自分たちが頑張っても終わっちゃうんで、子どもたちがやりたいと言ってもらうためにも自分らの待遇をしっかりして、いい仕事だな、かっこいいな、やってみたいなと思う仕事にしていきたかったんです。
子どものためだけではない「木育」
Q:子どもが木と触れ合い、木に学ぶ「木育」という言葉が最近使われてきていると思うんですけど、東京チェンソーズさんや木田さんは「木育」に対してどんな想いがありますか。

保育園の木育活動で丸太切り体験の様子(写真提供:東京チェンソーズ)
東京チェンソーズでも幼稚園・保育園の木育活動に協力して、植樹体験や丸太切りなどをやっています。木育を続けているところは子どもたちも木に詳しくなってくるし、イベントのときは嬉しそうだし、なんか自然のまま伸び伸びみたいな感じで…。子どものうちから木は楽しいと感じてもらえたら、木とか森から離れても、後で大人になった時に思い出すかもしれない。まったく知らないと森には近寄ってこないと思うけれども、子どもの頃、木に触れて楽しかったなとか、そういう思い出があるとまたこっちに帰ってくることもあると思うんで、子どもたちのいわゆる原体験というか、そういうものになってくれればいいと思います。さらに、先生方も変わってきていて、先生もそこの幼稚園に入ることで木育を知って木ってすごくいいなとか、森って気持ちいいなとかなってくるし、木育があるからここで保育士やりたいとか、そういう人も増えてきているという話もあるんです。木育って子どもたちのためだけではないという気もしています。

子どもたちが植樹した木
大都市東京でやる林業の世界
Q:東京でやる林業と郊外でやる林業に違いはありますか。木田さんが思う、都会である東京での林業の強みを聞かせてください。
地方で林業をやったことないので、ちゃんとわかってないんだけれども、東京でやる強みは、いろんな会社があって、経済活動が他の地方に比べて圧倒的に大きいことですね。新しい建物もどんどんできるし、その中に自然のものを取り入れたいという空気感もすごくあります。また、同じ東京なので、見に来やすいという利点もあります。こちらに来て実際に森の中を歩いて、森や木を見ることで、ものづくりのイメージを広げてくれる方も結構います。曲がっているところがある木や、変わった形の木などは市場で受け取ってくれないので、買い先も自分で探す必要があります。地方に比べたら東京は市場に出せない木でも面白いと思って買ってくれる会社やデザイナーさんたちが多いので、仕事が成り立ちやすいということが言えそうです。

普通は捨てられてしまう曲がった木や根っこだが…(写真提供:東京チェンソーズ)
Q:東京ならではのデザイナーさんとの出会いや、印象的だった活動はありますか。
木のいろんなところを使ってもらう活動の最初のきっかけは、枝を使いたいという話があったんです。都市部のビルの屋上で農園をやろうと活動している人たちがいて、その農園の畑の柵を作るときに、枝を使いたいということでした。いわゆる普通の木の板で作るのではなく、枝の曲がった形が変だったりする物を使って作った方が面白いねということで、その人から声がかかって枝をそこに出しました。その畑づくりのイベントに内装デザインの会社の人が来ていて、枝のこういうところ面白いねとか、山にはもっと個性的な形をした木がいっぱいあるんですよ、というような話をしました。その後、そのデザイナーの人たちが面白そうだからということで来てくれて、そこから始まっています。まあ、最初はそこの会社とあと何件かだったのが、だんだん広がってきていて、運というのもあるかもしれないけども、私たちも丸太以外の木も使いたいという気持ちがあったので、ちょうどいいタイミングで出会えたと思います。
林業の世界から見た「東京の自然」と「人」
Q:木や森が東京にとってどんな存在になってほしいですか。
東京に住む人にとって、森も木も当たり前の場所になってほしいです。実は東京の4割が森なんですよ。でも知らない人が多くて、森に行くとか、東京の木でなにかを作ってみるとか、あんまり意識してないと思うんですよ。だから東京の木を地元の木って思ってもらいたいし、地元の森ということで都心部から遊びに行く場所として考えてもらえたらいいなと思っています。海に行くのと同じ感じで、今日山に行ってみようかって言って、普通に来てくれればいいなと思っています。東京の人にとって森が当たり前だってなるとすごくいいなと思います。

東京チェンソーズが所有するMOKKIの森
Q:木田さん自身が思う林業の共生ってどんなことでしょうか。
森と人の共生というのをすごく考えています。都市部に住む人だけではなく、この辺に住む人も森とすごく親しんでいるかといったら、そうでもないんですよ。だから森と人、お互いの存在を認め合って、お互い存在するのが当たり前という関係性であるべきだと思います。どっちも当たり前にあって、遊びに行きたければ行くし、行きたくなければ行かないしというように、それぞれを認める。それだけでいいのかなっていろんなものが同時に対等にいるのが共生かなと思います。

山の中で行う企業研修の様子(写真提供:東京チェンソーズ)
(インタビュー:2025年6月)